
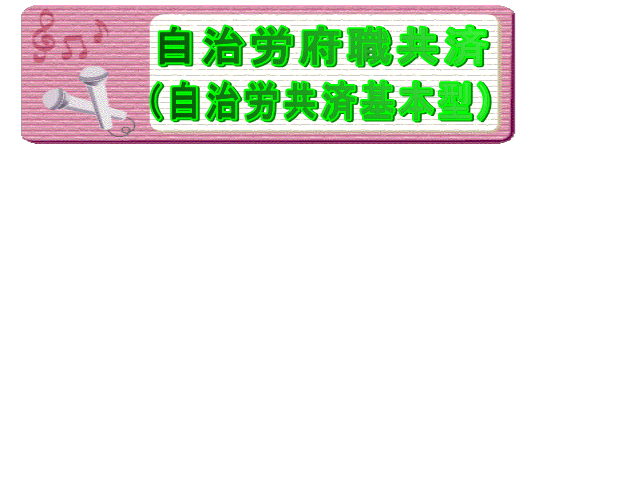

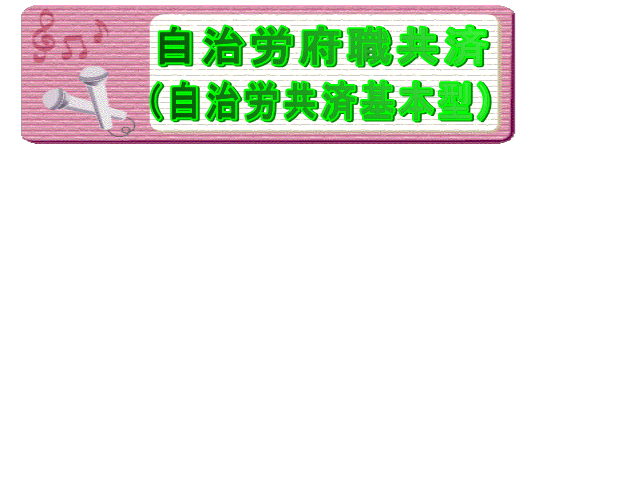
自治労府職共済は、組合員の自主福祉活動の一環として組合員の共済を図るとともに組織の強化を図る目的で、1973年12月20日第50回本部定期大会で共済規程を制定し、1974年1月1日から発足させました。組合費の中から共済事業特別会計を設けて運営し、自治労共済基本型に加入することにより再共済しています。
自治労府職共済の対象となる給付事由、その給付金額及び請求書、必要な添付書類は次表のとおりです。共済事由が発生した場合は、該当する組合員が申請者となり、「自治労府職共済 共済金支払請求書」に必要事項を記入し、必要書類を添付してください。請求書類は、分会・支部・単組を経由して本部福利厚生部まで提出となります。(組合員本人死亡の場合の申請者は所属単組・支部の単組・支部長となります。)住宅災害給付については、罹災した場合速やかに本部福利厚生部まで連絡を行い、給付金請求手続は他の場合と同様に行って下さい。
自治労府職共済給付金額と添付書類
《給付認定上の注意事項》
濉死亡給付
夽 配偶者、子、親については、扶養の有無を問わない。
㚙 配偶者とは、同居・別居に関係なく婚姻の届出のある者。
または、婚姻の届出はないが、同居し事実上婚姻関係の事情にある者とする。
奆 子とは、実子、養子、継子、義子とする。
死産または早産の場合、妊娠7ヶ月以上であれば子の死亡とし、双生児であれば2件として取り扱う。
㚖 親とは、組合員及び配偶者の親で、実父母、義父母、継親とする。
𦰩 その他の扶養親族とは、地方公務員共済組合その他組合員が所属する共済組合等の認定を受けた被扶養者とする。(配偶者、親、子を除く)
濉住宅災害給付
夽 親族の死亡とは、同居する6親等以内の血族および3親等以内の姻族が死亡した場合をいう。
夽「風呂の空だき」給付については、当該事実の発生に基づき、住宅災害給付申請を行ったが、「一部焼」の給付対象に至らなかった災害に給付する。
夽出産給付
夽多胎児出産については、人数分を給付する。
夽夫婦とも組合員の場合、それぞれ給付する。
夽就学給付
夽夫婦とも組合員の場合、それぞれ給付する。
濉退職給付
夽 退職とは、死亡給付の対象となる死亡退職を除き、退職により大阪府を離れる場合とする。ただし、再任用者については、再任用前の退職とする。
夽 組合員期間5年以上のものを対象とし、 期間計算は月計算による。
濉自治労共済基本型の退職給付(退職餞別金)と併給しない
濉再任用餞別金
濉給付については、再任用期間の通算年数とする。
なお、期間の計算は月計算で行い、1年に満たない月数は切捨てとする。
また、死亡給付と併給しない。
濉自治労総合共済基本型等の給付認定基準の準用
上記のほか、自治労総合共済基本型及び全労済慶弔共済の給付認定基準を準用する。